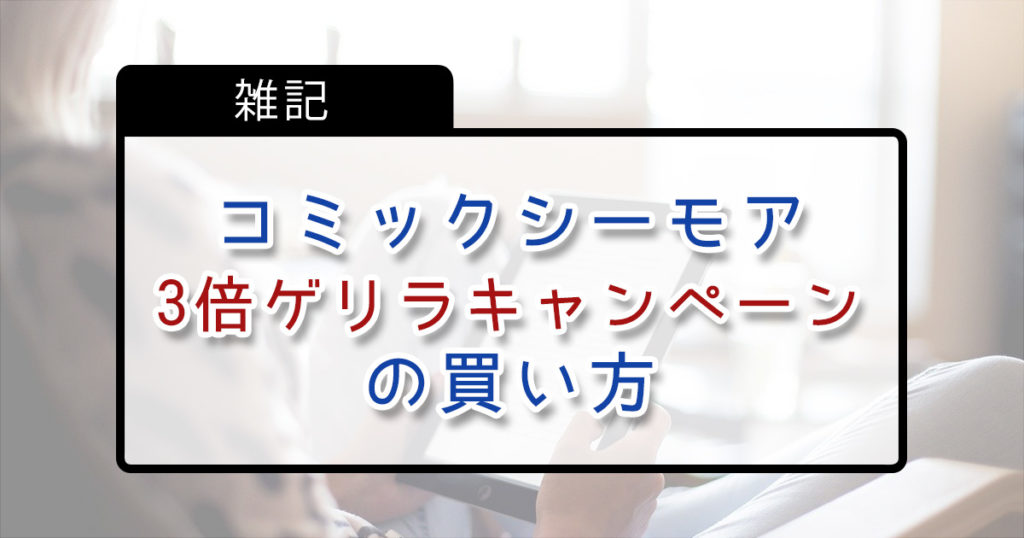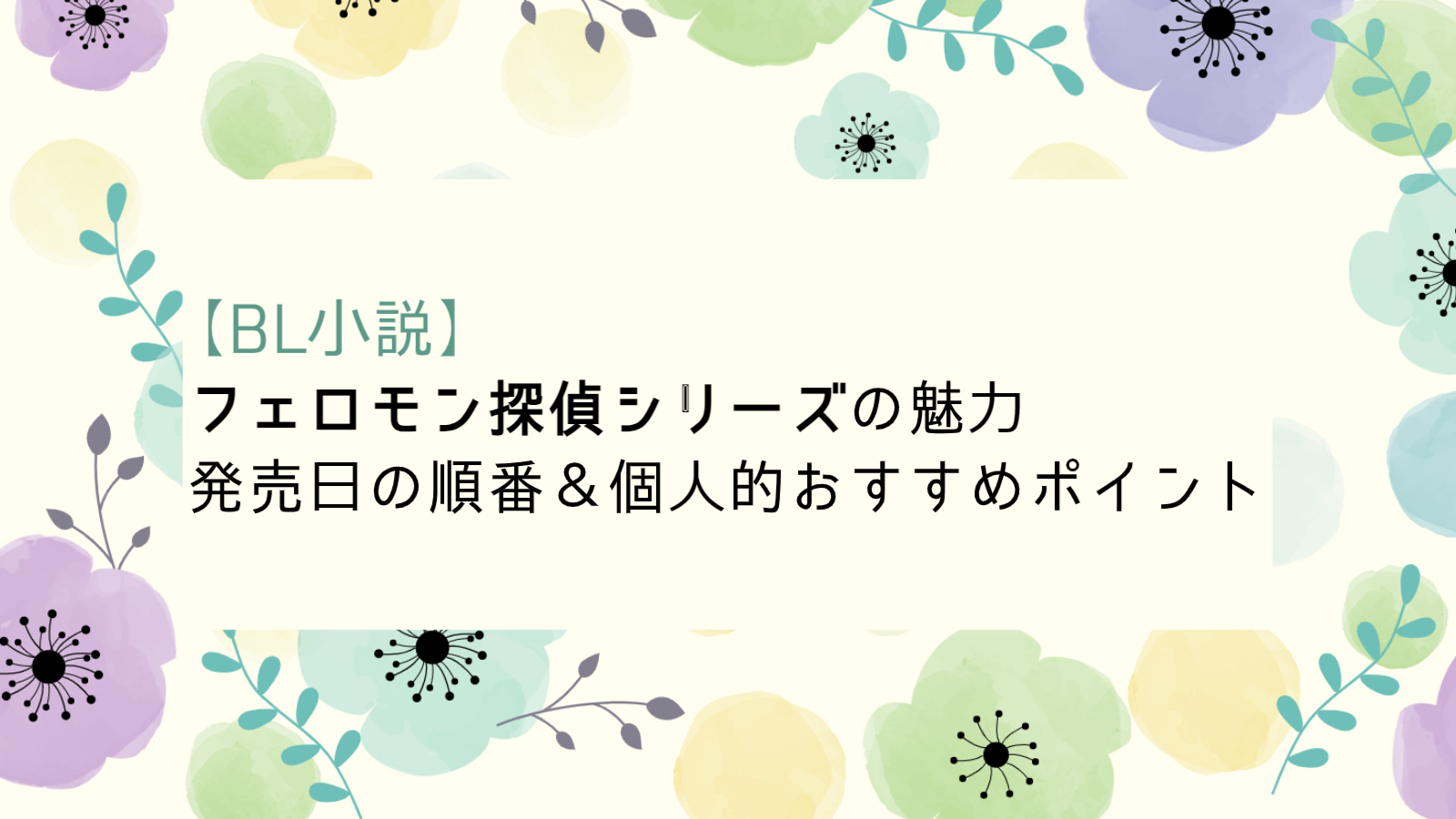(どこまで伏字にすれば良いか探り探りやっています。絵文字はPCだと表示がかわいくなかったので今回は【頭文字を片仮名一字】でやってみます。)
prskは「今までハマってきた中で一番やばいコンテンツだなあ」と日々感じています。(もちろん良い意味です)供給の早さとクォリティがエグすぎるんですよね。マイナージャンルで何年もやってきている人間には供給過多で最高に幸せです。
今までの人生「わーい久しぶりの食べ物だ! おいしい! うれしい!」って食べてたのが、「めっちゃ食べ物くる!! 全部おいしい!! 気が狂う!! うわあああああ!!」って感じになっています(?)
◆文化祭のこと
めっちゃかわいい。めっちゃかわいい。ネちゃんの「わたあめやさん」の響きで「ウヒーッ」ってなりました。エちゃんとミちゃんのために形のいいやつ取っておいてくれるんだ……カワイイね……。ワンツーもかわいいよぉ……君たち仲良しだね。いちゃいちゃを見せつけられて笑顔になってしまいました。(別に見せつけられてはいない)兄さんは見守ってくれている感じが本当~~にお兄さんで最高だなぁ……。
(もっと感想があったはずなのに出てくるのが最高にキモイものばかりなので泣きました)
文化祭、prsk教えてくれた友達と一緒に行こうとしていたのですがチケット外れてしまいましたTT 一般販売に賭けます。でも無理だろうなぁ~……。ただ、友達はフジョシじゃないので私の限界オタクっぷりを見せることにならなくてある意味良かったのかもしれない。
◆スタンプミッションのこと
スタンプミッションの「フレンド5人でじゃーにーをプレイ」ですが、フレンドさんの協力で無事クリアできてめちゃくちゃ感動しましたTT
まずは部屋を作って私と友達が入り、その後フレンドをウオオーッって招待しまくるという感じでやってみましたが、すぐに集まってくれましたTT しかも全員ルくん推しTT 最初に来てくれた人がルくんの「おや?」のスタンプ押してて「か、カワイイーッッ!!」ってなってました。
乱れ飛ぶルくんスタンプ、最高の部屋でしたTT(誤操作で解散が怖かったのでスクショは撮りませんでした)協力してくださったルくん推しのフレンドさんたち、センキューでした……世界は愛に溢れてる。
◆アナボのこと
神まにのアナボめちゃくちゃ嬉しい。急に来るからびっくりしますね。私は一曲に一人のアナボ交換と決めているので(聴ききれないから)めちゃくちゃ悩んだ末ルくんのと交換しました。美声すぎるだろ! って思いながらプレイしています。
◆Pixivのこと
先日Pixivに上げた小説ですが、たくさんの方に読んでいただけて本当にうれしいです。ありがとうございます。ブクマ・いいね・絵文字等とっても嬉しいです。
Pixivに投稿したのは久しぶりだったのですが、表紙がたくさんの中から選べるようになっていてびっくりしました。今まで「皆さん表紙凝っててすごすぎる! canvaとかで作ってるのかなぁ」って思ってました。絵文字システムも初めてだったのでびっくり&嬉しかったです。押してくださった方一人一人にハグをさせてほしい……。
次はラブコメのルツを上げたいなぁ~と思っています。もう書いてはいるのですが、書き出しが気に入らなすぎて全部書き直そうと思うのでもうちょっとかかりそうです。
SSも↓に一個置いておきます^^
僕が司くん達とワンダーランズ×ショウタイムとして一緒にやっていくと決まってから、数日が経った。 「類! 今日も一緒に帰るぞ!」 「……うん、いいよ。司くん」 あれから、学校帰りは毎日司くんと一緒だった。寧々も誘うと「司と一緒に帰ると疲れるから」と断られるため、いつも二人きりで道を歩いている。正直、居心地が良いとは言えない。司くんとショーについての話をするのはいい。楽しいか楽しくないかで考えれば、楽しいの方に針が振れる。しかし、元々他人と一緒に過ごすという行為自体が慣れていないというのもあり、司くんが上機嫌でマシンガントークを披露していると、時々わけもなく「一人にさせてくれ」と言いたくなってしまう。 「……というわけだ。ん? 類、聞いていたか?」 「ああ、聞いていたよ。ステージ裏の倉庫を貸してもらえることになったって話だよね」 「うむ! これで小道具や衣装の持ち運び問題は解決したというわけだ。まあ、他のステージの人たちと共同で使うことにはなるけどな」 司くんは、他のステージのキャストにどうやって交渉したのか、どんな人たちだったのかを僕に詳細に教えてくれている。しかし内容そのものは頭に入って来ず、司くんは人の懐に入るのが上手いんだな、という印象だけが残った。学校でもどこでも、司くんの周りには常に誰かがいる。自分とは違う生き物のように思えて興味深いところはあるが、僕の警戒心はなかなか消えてはくれなかった。 (まあ、あんな喧嘩、人生初だったんじゃないかなって感じだしね) 僕は一度、司くんに失望して「もう二度とこの人とショーなどしたくない」とまで思ってしまった。今までの人生、自分が他人にあんなに憤ったことも無かったし、他人に熱心に口説かれたことも無かった。よくあそこからここまで関係が修復できたものだと不思議な気持ちになってしまう。今となっては過去の話となるが、まだ心の奥底では司くんを信用しきれていないところがある。逆に、あんなことがあったのにこうして僕と平然と話ができる司くんが信じられないと思ってしまうほどだ。 「お、類。あそこのコンビニに少し寄ってもいいか」 「ああ、いいよ」 司くんが、僕のカーディガンの袖をくい、と引っ張る。司くんは時々こうしてボディタッチをはかることがあるが、無意識なのだろうか。揃って入店したコンビニで、司くんは真っ先にデザートのコーナーへと向かっていく。商品棚をひととおり見てシュークリームを手に取り、僕の方をぱっと振り向いて笑顔を見せた。 「あった! 妹の咲希がどうしてもこれを食べたいと言っていたんだ。お前と一緒に帰って助かったぞ!」 司くんはそれだけを言うと、レジへと向かった。シュークリームを一つと、何かホットスナックを頼んでいる気配がする。妹のためにスイーツを探していたことは分かったが、それがなぜ僕と一緒に帰っていたおかげなのだろうか? コンビニの外で待つことにした僕の横に、嬉しそうな顔の司くんが並ぶ。再び歩き始めた時、司くんが僕に何かの包みのようなものを差し出した。 「お前にやる。今日のお礼だ!」 にこにこと、音がしそうなほど上機嫌に笑っている。差し出されたものを受け取ると、数個のからあげが刺さった串だった。まだあたたかくておいしそうではあるが、僕がこれを受け取る理由が無い。 「いやいや、こんな、もらえないよ。僕は何もしていないのだし」 む、と明らかに不満そうに唇をつきだしている。そんな顔をされても困るのはこちらなのだが、司くんは僕が返そうとしているからあげ串をパーにした手のひらで拒否した。 「何を言う。類がいなければここの道は通らなかったんだぞ。だからお前のおかげというわけだ」 「え、なんで僕がいないとここの道を通らないの? 帰り道だろう?」 「オレの家に帰るには少し遠回りになるからな」 そうなんだ、と相づちをうつ自分の声が遠くに聞こえる。今までそんなことを一度も言っていなかったので知らなかった。司くんの家の位置を聞いたことがなかったので、てっきり一緒の方向なのだとばかり思っていた。 「遠回りなんてしなくていいのに。なんだか悪いよ」 「オレがお前と話したいからしていることなのに、そんなことを言うなよ。悲しくなるだろうが」 心臓がどくん、と大きく動いたのが分かった。司くんが嘘をついていたりおためごかしを言っていないことは、まっすぐオレンジの瞳が如実に語っている。まだ短期間しか一緒にいない相手にこんなことを思うのは、もしかしたらおかしいのかもしれない。それでも、司くんにはそう思わせる何かがあるように思えた。 「……でもやっぱり、これをもらってしまうのは流石に……」 「分かった! 遠慮させてしまったオレも悪いのだから、半分こにすればいい。まずは類、お前が先に半分食べろ。残りをオレがもらうから」 司くんは、またにこにこと笑っている。「まあ、それなら」と、自然と折れてしまう自分がいた。紙製の包みを開けて一つからあげを頬張ると、少し冷めてはいたがそれでもおいしかった。僕の様子を司くんが嬉しそうにまだ見ているので、咀嚼するのが少し恥ずかしい。 「はい、半分もらったよ」 「おう」 受け取った司くんが、僕よりも上品な仕草でからあげの半分を口に入れた。他人が口をつけたものでも躊躇無く食べられる人なんだな、と不思議な心地で見てしまう。「同じ釜の飯を食った仲」という言葉があるが、やはり食べ物を共有するというのは不思議なもので、司くんへの警戒心が減ったのを感じた。食べ終わった司くんはポケットティッシュを取り出したあと、「使うか?」と僕に差し出した。一枚もらい口の周りを拭いたのを「貸せ」と司くんが受け取って、自分の口を拭いたティッシュと一緒に小さな袋に入れた。 司くんは、仕草に育ちの良さが滲み出ている。男子高校生が、ハンカチとティッシュを常備していたり、ゴミを入れる袋を用意していたりするのだろうか。友人のいない僕には分からないが、少なくとも僕はかろうじてハンカチはあってもティッシュを持ち歩いてはいない。それとも、彼に妹がいるからその影響なのだろうか。 「じゃあ、オレはこっちだから。話の続きはまた明日だな、類」 交差点で、司くんは手を振って僕とは違う方向へと歩いて行く。「うん、また明日」と小さく手をふりかえしながら、少しさみしいと思ってしまった。昨日までは無かった自分の感情に困惑してしまう。なんだか、徐々に司くんへの興味が湧き出てきている気がする。今日は不思議な日だな、などと思いながら、自分の家へと向かう道を歩き出した。 *** ――なんて、そんな風に思っていた時期もあったんだけどね。 僕の部屋のソファで寝ている司くんの寝顔を眺めながら、数ヶ月前の自分のことを考えていた。あの頃のツンツンしていた僕などとうに消え去ってしまって、今はもう司くんと片時も離れたくないと思っている。長い睫が影を落としている頬を指先でなぞると、司くんはくすぐったそうに肩をすくめてからゆっくりとまぶたを開けた。司くんのまっすぐな瞳はあの頃と変わっていないのに、より輝きを増しているように思えるのは、きっと僕がこの人に恋をしているからだろう。 「類。ごめん、いつのまにか寝てたんだな」 ふわりと笑った顔を、愛おしいと思う。傲慢なほどきれいな司くんの魂が、ずっと僕を惹きつけてやまない。 「おはよう、司くん」 「ん」 司くんがブランケットを上げて隣に来るように誘うので、もぞもぞとソファに寝転がる。男子高校生二人が寝るには明らかに狭いソファの上でぎゅうぎゅうになって抱き合いながら、二人でくすくすと笑った。 「類、今日の昼何か食べたいものはあるか?」 「じゃあ、司くんを食べようかな」 「それはさっき食べただろ」 ふふ、と司くんが呆れたように笑っている。たったの数ヶ月で、僕と司くんの関係は大きく変わってしまった。飛び越えた垣根は見る影も無く遠くに去り、今は真綿で包まれたような暖かい空間があるだけだ。こういうのを幸せと言うのだろうかと、時々無性に泣きたくなってしまう。 「それ以外ならなんでもいい」 「じゃあ、コンビニのからあげ串食べたい」 「類、それ好きだよな。では買いに行くか!」 好きなのはからあげじゃないんだけどね、と言いたいのを飲み込んで、二人で外へ出た。司くんたちとやるショーが何よりも好きだし、僕は司くんのことが大好きだ。あの時行ったコンビニは変わらず迎えてくれて、僕はまたあの日のことを思い出していた。 おしまい